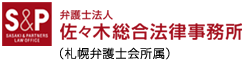![]()
平成26年度第2回札医学術講演会
「医師に要求される医療水準と診療ガイドライン」
~医師は診療ガイドラインどおりの治療をしなければならないのか?~
講演から一部抜粋
- 1 医療事故とは?
医療に関わる場所で、医療の全過程において発生するすべての人身事故である(厚生労働省リスクマネージメントスタンダードマニュアル作成委員会)。医療提供者の過失の有無は問わず、不可抗力と思われる事象も含む(過失があるのが医療過誤である)。医療事故を無くし、発生した医療事故を早期円満かつ公平に解決することは、医療関係者のみならず国民全体の願いだが・・・・・・・・「公平な解決」の内容が問題となる。
- 2 整形外科の事案で医療事故が発生すると患者側はどのような主張をするのか?
- ① そもそも手術適応がなかった
- ② 手術適応はあったが術式に問題があった。または手技ミスがあった。
- ③ 術後管理に過失があった
- ④ 行うべき検査を行っていない
*上記4項目について医学文献等十分な根拠資料を準備し、根拠資料に基づく主張がされることが多い!
- ⑤ 仮に治療行為そのものについては医師の過失が全く無く、不可避的な合併症によるものであったとしても、合併症発症のリスクについて説明を受けていない。検査の必要性についても説明を受けていない。→患者側主張の最後の砦!
- 3 医事紛争予防、対応の基本的心構え
- ① 医療側と患者側さらには裁判所の常識は異なることを認識する必要がある。
→合併症、偶発症は不可避それとも手技ミス?
→医療慣行と医療水準は異なる! - ② 医療側の善意が必ず患者側に伝わるとは限らないこと→善意が裏目に出ることもある。
- ③ 医療側の相手は患者本人だけではないこと
→突然現れて医療側を非難する遠方居住の親族など - ④ すべてを自分一人で背負わないこと→モンスター患者、家族への対応の場合など
- ① 医療側と患者側さらには裁判所の常識は異なることを認識する必要がある。
- 4 医療裁判、医療訴訟とは?
医療過誤、つまり、医師の過失の有無を、民事訴訟法に定められた手続きによって、裁判所が証拠に基づいて判断するものである。
- ① 事実認定
診療経過(診察、投薬、検査等)の確定 - ② 判断、評価
診療行為に注意義務違反行為すなわち過失があるか、因果関係があるかを判断
- ① 事実認定
- 5 医師の注意義務の具体的内容
- ① 医療水準に見合った医療行為を行うこと
→医療水準は、医師が個々の患者に対して負っている診療上の注意義務を法的に判断する際の基準である。 - ② 患者の自己決定権を侵害しないこと
→診療当時の医学的知見をふまえたものでなければならない。説明義務における医療水準が問題となる。
- ① 医療水準に見合った医療行為を行うこと
- 6 医療水準についての裁判所の考え方
- ① 医師の注意義務の基準となるべきものは、診療当時のいわゆる臨床医学の実践における医療水準である。
- ② 医療水準は、全国一律に絶対的な基準として考えるべきものではなく、当該医療機関の性格、地域の医療環境の特性等の事情を考慮して決める。
- ③ ある治療法に関する知見が類似の特性を備えた医療機関に相当程度普及しており、当該医療機関がその知見を有することを期待することが相当と認められる場合には、その知見が当該医療機関にとっての医療水準である。
→従来の基準よりも厳しい。特に、基幹医療機関には、厳しい認定が下されることになる。 - ④ 医療水準は、平均的医師が現に行なっている医療慣行とは必ずしも一致するものではなく、一般的に行なわれているというだけでは足りず、そのような一般的な慣行が医学的に合理性を有することが説明できなければならない。
- ⑤ 設備の制約や経験不足などから、自らの施設で医療水準が確保できないときは、患者を受け入れて適切な治療を実施できる病院に転医させる義務がある。
- ⑥ 医学的知見の進歩に伴って上昇する。
- 7 証拠は何か?
(1) 事実認定の場面
- ① 医療記録(カルテ、看護記録、各種検査記録)
- ② 解剖結果、鑑定結果
- ③ 医師、看護師等の尋問
鑑定、意見書、医学文献(診療ガイドライン、治療指針、添付文書、論文) - 8 診療ガイドラインとは
ガイドラインとは、一般的に「ある目的実施を伴う誘導指標・指導目標」を示し、ある組織・団体における個人、または全体の行動に関し、「守るのが好ましいとされる基準となるもの」である
医療における診療ガイドラインは「標準的な治療法」を説明した文書であり、その時点における知見をまとめた「実質上のスタンダード」である。 - 9 ガイドライン、添付文書についての医師と裁判官の意識の差
- ① ガイドラインについて
医師の常識→複数ある治療手技の一例を示す内容
裁判官 →現時点における臨床上の水準を示すものでは?
唯一最良の治療法ではないのか? - ② 医薬品添付文書について
医師の常識→記載内容は必ずしも臨床と合致しない。
裁量で増減は当然である。
裁判官 →記載に合致しない投薬は医療過誤では?
- ① ガイドラインについて
- 10 現代社会では、専門家すなわちプロは、素人が理解できる、素人でも納得できる内容の仕事をしなければならないのであって、その意味では「医療水準」という概念は、「法律的批判に耐えうる医療水準」と考えざるを得ない。現実に訴訟となった場合、医学の素人である裁判官は、医薬品の投与については、当該医薬品の添付文書の記載内容を重視するし、治療法については、各種ガイドラインや学会の論文を重視する傾向がある。
しかし、民事訴訟法247条は、「裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。」と規定しているが、何故、医療裁判では違うのか?→医療裁判が高度の専門知識を要するからである。 - 11 診療ガイドラインは絶対か?
診療ガイドラインから外れた治療をした場合、過失となるのか?
→裁判官の判断は、あらゆる要因を踏まえて行うものである。診療ガイドラインの基準から外れるだけでは直ちに過失と判断されるわけではない。しかし、裁判官は、診療ガイドラインを高く評価しがちであるから、グレードAの治療と異なる場合には十分注意する必要がある。
*裁判官はガイドラインを重要な証拠として扱う可能性が高い! - 12 診療ガイドラインについての裁判所の認識が顕著の事例(さいたま地判平成26年1月30日 判例時報2231号74頁)
「ガイドラインは、専門家が議論し有効性と安全性を検討したうえでまとめられ、策定時点における望ましい治療法あるいは標準的治療法を示すものである以上、医療水準を認定する証拠として証拠価値が高いということができる。」
→前交通動脈の破裂脳動脈瘤に対するクリッピング手術において、脳卒中治療ガイドライン2009の記載内容から、一時クリップを使用することが医療水準として一般的に認められた注意義務になっていないとして、患者側の主張を斥けた事例 - 13 診療ガイドラインと異なる診療行為が注意義務違反とならないためには?
- ① 事例の特殊性・例外性
→当該患者の症例が、ガイドラインに記載される一般的な症例と異なる。特殊な点がある。 - ② 治療の合理性
→担当医師が選択した診療行為に医学的なエビデンスが存在する。 - ③ その他、診療ガイドラインを排除すべき理由がある
→患者に緊急性を要する場合
* 担当医師の類を見ないほどの実績はどうであろうか? - ④ 患者へのICは必要か?
→必要である。
- ① 事例の特殊性・例外性
- 14 具体的事例についての検討①(脳動脈瘤の手術適応が争点となった事例)
- (1)Xは(女性53歳)、平成15年2月2日、A大学病院での検査の結果、脳の左右に未破裂脳動脈瘤が1つずつあることが確認され、同年8月15日にYに入院し、主治医から手術の概要について説明を受けて手術承諾書に署名押印し、同月18日に左側脳動脈瘤のコイル塞栓術を受けた後、同月22日午後1時30分から午後4時50分まで右側脳動脈瘤のコイル塞栓術を受けたが、同日午後8時、嘔吐、眼球運動不可、左上下肢不動等の症状が発現し、CT検査の結果、看過できない血腫の増大(脳内出血)が確認されたため、同日午後10時4分に開頭手術を受けた後、同年12月24日に退院したが、平成16年4月1日に身体障害者手帳の交付を受け、平成19年10月1日に脳梗塞による左上肢機能障害(2級)及び左下肢機能障害(4級)を内容とする身体障害者手帳の交付を受けた。
- (2)本件の争点は何か?
- ① Xの右側脳動脈瘤は手術適応があったか?
手術して良かったのか?
経過観察という選択肢もあったのではないか?
→どのような基準をもとに判断されるのか? - ② 保存的治療法について説明しなかったことの過失の有無
→説明責任の根拠は?
本件事案における説明の範囲はどこまで? - ③ 説明義務違反と損害との間の因果関係
→患者は説明を受けていれば手術を受けなかったのか?
- ① Xの右側脳動脈瘤は手術適応があったか?
- (3)本件の手術適応に関する裁判所の判断
(仙台地判平成25年1月17日 裁判所ウエブサイト)
日本脳ドック学会作成の「脳ドックのガイドライン」(2003年版)によれば、無症候性未破裂脳動脈瘤では最大径が5㎜前後より大きく、年齢がほぼ70歳以下でその他の条件が治療を妨げない場合には、手術的治療が勧められるとされており、多発性脳動脈瘤は単発性のものよりも破裂のリスクが高い。Xの右脳動脈瘤の大きさは、正面からの測定結果が6.2㎜×4.4㎜、側面からの測定結果が4.3㎜×4.9㎜であり、最大径が6.2㎜あって5㎜以上であり、Xの年齢、Xの右脳動脈瘤が多発性のものであることから、Xに手術適応があるとしたYの判断は当時の医療水準に照らして不合理とはいえない。 - (4)医師は保存的治療法について説明すべきであったか?
病院側の主張→脳動脈瘤に対する治療は外科的治療のみであり(コイル塞栓術、クリッピング手術)のみであり、他に保存的療法というべきものは存在せず、原告が保存的療法として主張する薬物療法や食事療法、運動療法などによっては脳動脈瘤の破裂を予防することはできないので、外科的治療以外の選択肢について説明すべき義務はない。
裁判所の判断→経過観察を行うこと自体が脳動脈瘤に対する治療効果を有しないことは被告主張のとおりであるが、他方で、脳動脈瘤の破裂リスクは大きさ等の事情によってまちまちである上、外科的治療には合併症や後遺症といったリスクが一定程度あることからすれば、脳動脈瘤に対して経過観察をすることも有用な選択肢の一つであるといえる。平成15年当時の脳ドックのガイドラインにおいても、脳動脈瘤の大きさが5㎜前後よりも大きい場合等に手術的治療が勧められるとしつつも、手術しない場合は1年間隔で経過観察を行うなどとされており、脳動脈瘤につき経過観察を行うことが選択肢の一つとされている。
- (1)Xは(女性53歳)、平成15年2月2日、A大学病院での検査の結果、脳の左右に未破裂脳動脈瘤が1つずつあることが確認され、同年8月15日にYに入院し、主治医から手術の概要について説明を受けて手術承諾書に署名押印し、同月18日に左側脳動脈瘤のコイル塞栓術を受けた後、同月22日午後1時30分から午後4時50分まで右側脳動脈瘤のコイル塞栓術を受けたが、同日午後8時、嘔吐、眼球運動不可、左上下肢不動等の症状が発現し、CT検査の結果、看過できない血腫の増大(脳内出血)が確認されたため、同日午後10時4分に開頭手術を受けた後、同年12月24日に退院したが、平成16年4月1日に身体障害者手帳の交付を受け、平成19年10月1日に脳梗塞による左上肢機能障害(2級)及び左下肢機能障害(4級)を内容とする身体障害者手帳の交付を受けた。
- 15 具体的事例についての検討②(肝がんについての検査の有無が争点となった事例 仙台地判平成22年6月30日 裁判所ウエブサイト)
- (1)X(女性 死亡時79歳)は、平成12年9月、Y医師から初期の肝硬変と診断された(B型、C型肝硬変ではない。)。
Y医師はXの来院ごとにGOT、GPT、γーGTP及び血小板数を測定したがいずれの数値も正常範囲内であり、くも状血管腫等の身体症状も見られなかった。平成18年8月8日、呼吸苦、心不全による食欲低下等により、入院し、胸部造影CT検査を実施したところ、肝臓内にlow density(黒い領域) が認められ、精査の結果、原発性の肝臓がんであることが判明した。
平成18年10月23日、Xは、多発性肝臓がんにより死亡した。 - (2)診療ガイドラインの位置づけについての裁判所の考え
診療ガイドラインは,その時点における標準的な知見を集約したものであるから,それに沿うことによって当該治療方法が合理的であると評価される場合が多くなるのはもとより当然である。
もっとも,診療ガイドラインはあらゆる症例に適応する絶対的なものとまではいえないから,個々の患者の具体的症状が診療ガイドラインにおいて前提とされる症状と必ずしも一致しないような場合や,患者固有の特殊事情がある場合において,相応の医学的根拠に基づいて個々の患者の状態に応じた治療方法を選択した場合には,それが診療ガイドラインと異なる治療方法であったとしても,直ちに医療機関に期待される合理的行動を逸脱したとは評価できない。
そして,肝癌診療ガイドラインにおいてサーベイランスの至適間隔に関する明確なエビデンスはないとされており,推奨の強さはグレードC1(行うことを考慮してもよいが十分な科学的根拠がない)と位置づけられていることからすれば,サーベイランスの間隔については一義的に標準化されているとまでは認めがたいのであるから,上記間隔については医師の裁量が認められる余地は相対的に大きくなるものと解される。
そこで,Y医師がどの程度の間隔でサーベイランスを行うべきであったかを検討するに,肝癌診療ガイドラインにおいて非ウイルス性の肝硬変は肝細胞癌の高危険群とされ,6か月に一回の超音波検査及び腫瘍マーカーの測定が推奨されている。 - (3)本件についての裁判所の結論
Xの肝硬変は発癌リスクが否定されるものではなかったことに加え,肝硬変の前段階とされる慢性肝炎であっても発癌リスクが相当程度認められることからすれば,Aの肝硬変が初期のものであったとしても,Y医師がXに対して肝硬変と診断してから一度も超音波検査等を実施しなかったことが相応の医学的根拠に基づくものとは評価しがたい。
医療行為において医師の裁量を尊重する必要があること及び肝癌診療ガイドラインが絶対的な基準ではないことを考慮してもなお,Y医師は,Xに対し,肝癌発見を目的として6か月間隔で腫瘍マーカー及び超音波検査を実施し,腫瘍マーカーの上昇や結節性病変が疑われた場合には造影CT検査等を実施すべきであったというべきである。
- (1)X(女性 死亡時79歳)は、平成12年9月、Y医師から初期の肝硬変と診断された(B型、C型肝硬変ではない。)。
- 16 具体的事例の検討③(開業医に急性脳症の発症を疑って患者を高度な医療を施すことのできる適切な医療機関へ転送すべき義務があるとされた事例 最判平成15年11月11日 判例時報1845号63頁)
「開業医が、その下で通院治療中の患者について、初診から5日目になっても投薬による症状の改善がなく、午前中の点滴をした後も前日の夜からのおう吐の症状が全く治まらず、午後の再度の点滴中に軽度の意識障害等を疑わせる言動があり、これに不安を覚えた母親が診察を求めたことなどから、その病名は特定できないまでも、自らの開設する診療所では検査及び治療の面で適切に対処することができない何らかの重大で緊急性のある病気にかかっている可能性が高いことを認識することができたなど判示の事情の下では、当該開業医には、上記診察を求められた時点で、直ちに当該患者を診断した上で、高度な医療を施すことのできる適切な医療機関へ転送し、適切な医療を受けさせる義務がある。」→連日の受診、1日に2度の来院患者については注意! -
17 厚生労働省平成19年5月「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」からの抜粋
- ① 家族が患者の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、患者にとっての最善の治療方針をとることを基本とする
- ② 家族が患者の意思を推定できない場合には、患者にとって何が最善であるかについて家族と十分話し合い、患者にとっての最善の治療方針をとることを基本とする。
がんの終末期に心肺蘇生術を試みずに安らかな最期を迎えること(DNR Do Not Resuscitate)について、患者家族が具体的内容を十分理解していない事案が頻発している。→ガイドラインに沿った十分なコミュニケーションが必要となる。 -
18 医療事故調査制度(平成26年6月18日成立の改正医療法)について
病院等管理者は、厚生労働省令で定める医療事故(現時点では内容未確定)については、医療事故調査・支援センターに届けること、死亡の原因について医療事故調査を行うこと、医療事故が発生した病院等の管理者又は遺族から、当該医療事故について調査の依頼があったときは、必要な調査を行うことができることや、医療事故調査支援センターは、第1項の調査を終了したときは、その調査の結果を同項の管理者及び遺族に報告しなければならない旨規定されている。
モデル事業(診療行為に関連した死亡の調査分析モデル)同様に、「標準的外来診療行為」「手術における標準的手技」等の基準によって、診療行為の内容が事後的にチェックされる機会が増大することになる! - 19 まとめ
- ① 医師の注意義務が、医療水準に見合った医療行為を行うことと、患者の自己決定権を侵害しないことの二つであることを再認識すること
- ② 医療水準に見合った医療行為を行ったか否かの判断において、診療ガイドラインが、各種文献の中でも最も重視されていることに留意すべきである。
- ③ 医療水準を満たした診療とICについて常に意識した診療を行うべきであるが、ICの事実を記録しておくことを心がけておくべきである。また、終末期医療においてもICの重要性を忘れてはならない。
- ④ 患者の転送義務や転医勧告義務も医療水準の問題であることを認識すべきである。