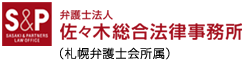講演日 平成30年10月23日
札幌市医師会医療安全研修会
最近の医事紛争の傾向と対策
~医療界と法曹界の相互理解を深めるために~
- 医師と法律家との間には思考方法や用語の理解について食い違いがあり、医療を巡る紛争解決のためには、医師と法律家との間に共通の基盤や相互理解が形成される必要がある。
医師が、法律家、特に裁判所や患者側弁護士の思考方法等を十分理解し、日常の診療行為を行うことは、医療事故(本講演では、「医療事故」は、「医療に関わる場所で、医療の全過程において発生するすべての人身事故、医療の過程において患者に発生した望ましくない現象」という定義で使用する。したがって、医療提供者の過失の有無は問わず、不可抗力と思われる事象も含むことにご留意いただきたい。)発生防止及び医療事故発生後の無用な紛争発生を回避する上で有益であると考える。近年、各地で医療界と法曹界の相互理解を深めるために、シンポジウム開催等さまざまな取り組みがなされているところであり、医療界と法曹界という2つの専門分野で、医療事故を接点として現れる思考方法などの相違点について認識を新たにしていただくことが必要である。
- 合併症と過失
(1) 医療界で使用されている「合併症」という言葉には以下の2つの意味があるが、本稿では②の意味で使用する。
- ① 疾患が前提となって生ずる続発性の病態・病変・疾患
- ② 疾患に対する内視鏡や手術などの検査あるいは治療に伴って、ある確率で不可避に生じる病気や症状
患者(53歳の女性)が右側脳動脈瘤のコイル塞栓術を受けた後、脳梗塞が発症し、左上肢機能障害(2級)及び左下肢機能障害(4級)の後遺障害が残ってしまった事案(以下「冒頭事案」)を例に考えるなら、医師は、コイル塞栓術の後に脳梗塞が発症したことは、合併症であると患者に説明する。
しかし、法曹界の立場からは「合併症」という法律用語は存在しないのであって、合併症は、医師に過失がある医療事故か無過失の医療事故のいずれかとなる。
冒頭事案のように手術後に重篤な後遺障害が残るという患者にとって望ましくない現象が発生した場合に、当該現象が合併症によるものである場合、医療側は、合併症である以上は責任がないと考えるが、患者側は、合併症は医師の過失に基づいて発生するものと考えることが多く、ここに紛争発生の素地がある。
患者にとっては納得できない合併症が発生し、医療機関と患者側で話し合いが行われても解決に至らない場合、最終的には裁判で決着をつけることになる。
(2) 裁判には、民事裁判と刑事裁判がある。
- ① 民事裁判
金銭の支払請求・物の返還請求などの民事責任の追及を目的とする。
当事者は原告と被告である。
- ② 刑事裁判
検察官が犯罪事実があるとして起訴し、犯罪者に刑罰(懲役刑、罰金刑等)を与えるための刑事責任の追及を目的とする。
当事者は検察官と被告人である。
医師の方はよく誤解されているが、民事裁判で被告が損害賠償を命じられても、そのことで刑罰は受けない。民事と刑事は基本的には全く別の手続きであり、民事裁判で、医師の過失が認められても、自動的に刑事裁判に移るということもない。
(3) 治療行為によって悪しき結果が発生したというだけでは責任を負わない。責任を負うのは、治療行為に過失が認められた場合に限られ、これを「過失責任主義」という。
過失というのは、「注意義務」を課せられた人間が、その注意義務に違反することであり、自動車運転を例に考えれば、運転者が前方横断歩道上で歩行者を跳ねた場合、歩行者が横断することについて予見可能性があるし、横断歩道手前で停止すれば歩行者を跳ねてしまうという結果を回避することが可能であるという構成になる。
つまり、①予見可能性+②結果回避可能性が過失(注意義務違反)の判断基準なのである。しかし、自動車運転の場合には、横断歩道手前で停止したり徐行すればよいのだが、医療では、死亡や重大な機能障害等の悪しき結果が生じる可能性のある手術を行う場合、悪しき結果が生じる可能性を予見することはできるし、手術をしないことで悪しき結果が生じることを回避することができるが、患者の状態によっては手術を避けられない事態に対応しなければならない。この意味で、医療行為の過失を自動車運転の過失と同じ法制度で規律すること自体に無理があると私は考えている。
(4) ところで、民事裁判と刑事裁判で過失の内容は異なるのであろうか?
裁判所の考えは、次のとおりである。
「予見可能性を前提とする結果回避義務違反であるという点では、民事も刑事も同じである。しかし、法律家の実務感覚では、刑事上の過失は国家刑罰権の発動の前提であって、刑法は謙抑的であるべきとの考えに基づき、刑罰を科す必要のある重い注意義務違反である。
これに対して、民事上の過失は、損害を金銭賠償する場合の根拠となるものであって、加害者と被害者との間における公平あるは平等を保つために被告に損害を賠償するという責任を負わせることについて、合理性、妥当性が認められれば過失といっても良い。」
裁判所は福島県立大野病院事件で、「臨床に携わっている医師に医療措置上の行為義務を負わせ、その義務に反したものには刑罰を科す基準となり得る医学的準則は、当該科目の臨床に携わる医師が、当該場面に直面した場合に、ほとんどの者がその基準に従った医療措置を講じていると言える程度の、一般性あるいは通有性を具備していなければならない。」と判示している。癒着胎盤の(用手)剥離を行っている最中に剥離面から大量出血が生じることを予見した医師は、どのような措置をとるべきであるのか、という点に関する「医療準則」は、「臨床上の標準的な医療措置」として行われていた内容すなわち「医療慣行」と一致する、と判断された。つまり、医師が医療慣行に沿った医療行為を行っている限り、刑事上の過失が認められることはない。
- 民事上の過失の内容について
(1) 民事上の過失の内容はどうであろうか。最高裁昭和36年2月16日判決は「いやしくも人の生命及び健康を管理すべき業務(医業)に従事する者は、その業務の性質に照し、危険防止のために実験上(*実際の経験上)必要とされる最善の注意義務を要求される。」と判示し、多数の最高裁判決は、「注意義務の基準となるべきものは、診療当時のいわゆる臨床医学の実践における医療水準である。」と判示しており、医師の注意義務の基準となるべきものが「診療当時のいわゆる臨床医学の実践における医療水準である」ことが確定した判例の立場になった。なお、最高裁平成8年1月23日判決は、「医療慣行に従った医療行為を行ったというだけでは、医療機関に要求される医療水準に基づいた注意義務を尽くしたことにはならない。」旨判示しているので、民事裁判では、医師にとっては刑事上の過失よりも厳しい注意義務が課されることになる。
裁判所によれば、「不可避の合併症」とは、最善の注意義務を尽くしても発生し得る「合併症」をいい、裁判で問題となるのは、最善の注意義務を尽くしたかどうかである。「合併症」であっても、そのすべてが当然に無過失とはならないのである。
(2) 医療側は、裁判所の考える「過失」に関して以下の疑問を呈している。
① どこまでが合併症で、どこからが過失なのか?
同じような事故なのに、片や医療側に責任があり、片や責任がないという判断がされているのでは?
② 法曹側によれば、医療における過失は、やるべきことをやらなかったとか、やってはいけないことをやったという、そのような表現で説明がされているが、問題は、そのやるべきだとか、やってはいけないというのを、誰が、どのように決めているんだというのはよく分からない。
③ 法的にどうかは置いておいても、医療としてはその段階でそういう対応をすべきだったということは、医療関係者、医療従事者の中にコンセンサスがある。
④ 法曹側は、「この時点で」「この点で」と言うが、医療側は患者の様子を点で見ることはなく、すべて連続してみているので、線なのか点なのかというのが非常に問題になる。
(3) そもそも、医師の注意義務の基準となる「医療水準」は誰がどのように決めるのであろうか。
民事裁判では、最終的には「判決」という形で裁判所が決定することになるが、裁判所は次のように述べている。
「私ども裁判官は間違いのない判断をしようと思っているのですが、いかんせん自分で経験したことではないし、正直言って素人ですから、裁判の場で、しっかりとした正しい議論ができていることが重要だと思っています。我々裁判官は、十分な情報が出されていればそんなに間違った判断はしていないと思っていますが、やはり必要な情報が出てこないと、裁判に出された情報を基に判断せざるを得ません。」
(4) 裁判所の、判断評価の基となる情報(証拠)とは、以下のものである。
① 裁判所による鑑定、医師の意見書
② 医学文献(診療ガイドライン、添付文書、論文)
上記の情報のうち、診療ガイドラインについての医療側と法曹側(裁判所)の意識の差は顕著である
裁判所は次のように述べている。
「医療事故発生時の医療水準を認定するための客観的な資料として、当事者からいろいろな医療文献を出していただくのですが、どれが権威のある文献かというのは法律家から見ると非常に分かりにくい。一方、ガイドラインは、その疾患の治療に専門的に当たっておられる大勢の先生方が、議論して、有効性と安全性を検討したうえでまとめられるというもので、策定時点における望ましい治療、あるいは標準的治療法を示すものというように法律家からは見える。
特定の患者についてガイドラインが妥当しないという事情があるのであれば、裁判手続きの中で分かりやすく裁判所に説明して欲しい。」
かように裁判所は診療ガイドラインを権威のある文献と位置づけているが、我々医療側弁護士や医療側は、診療ガイドラインは医学文献の一つにすぎず、絶対視することは避けるべきであると機会あるごとに主張している。
しかし、この主張に対する裁判所の考えは次のとおりである。
「先ほど〇〇先生から医療水準の認定に当たっては、ガイドラインだけではなく、その他の医学的文献や医学的知見を総合して判断する。その中の一つにガイドラインが位置付けられるということをおっしゃっていただいて、まさにそのとおりだと思っております。ガイドラインの記載と異なる合理的な理由というのをやはり分かりやすく説明していただく必要があろうと思っております。ガイドラインの一般的な性質というのはもちろんあろうかと思いますけれども「一般的な性質だからガイドラインは医師に対して特定の判断を義務付けるものではありません。」というだけの抽象的な反論にとどまって欲しくはないと思っております。当該ガイドラインと異なる医療行為をした以上は、当然何らかの合理的理由があったはずですので、それを医学的根拠を基にご説明いただくことが必要なのではないかと思っております。」
以上のとおり、裁判官の判断は、あらゆる要因を踏まえて行うものであるので、診療ガイドラインの基準から外れるだけでは直ちに過失と判断されるわけではなさそうではある。しかし、裁判所の上記各発言を見る限り、裁判所は、診療ガイドラインを高く評価しがちであるから、基準から外れた診療については説明を求められることに留意すべきである。
(5) 診療ガイドラインについて、医療側は以下のように主張している。
① とんでもない診療をしているというお医者さんも中にはいるのでそういうことをまず排除しようというので、標準的な治療を示してこれは明らかに標準的な治療とは異なりますよということを示すこともガイドラインの大きな役割であり、ガイドラインを用いて訴訟されるというようなことを作る側は想定していない。
② ガイドラインができたから常にそれが一般に流布して実施されているわけではない。
③ 「本ガイドラインが今後の肝細胞がんの診療に大いに役立つものと信じるが、臨床の現場での判断を強制するものではないし、医師の経験を否定するものでもない。本ガイドラインを参考にした上で、医師の裁量を尊重し、患者の意向を考慮して個々の患者に最も妥当な治療法を選択することが望ましい(肝癌診療ガイドライン2005前文)」と記載しているではないか。
④ 本ガイドラインは脳ドック実施者を対象に,脳ドックの水準と有効性のより一層の向上を目指して現時点における知見に基づいて推奨される指針を示す(脳ドックのガイドライン2003)
(6) しかし、裁判所は、医療側の主張に理解を示していない。
冒頭事案で、患者側は、「そもそも右脳動脈瘤の大きさからして本件は手術適応がなかった」と主張したが、裁判所は、「日本脳ドック学会作成の「脳ドックのガイドライン」(2003年版)によれば、無症候性未破裂脳動脈瘤では最大径が5㎜前後より大きく、年齢がほぼ70歳以下でその他の条件が治療を妨げない場合には、手術的治療が勧められるとされており、多発性脳動脈瘤は単発性のものよりも破裂のリスクが高い。Xの右脳動脈瘤の大きさは、正面からの測定結果が6.2㎜×4.4㎜、側面からの測定結果が4.3㎜×4.9㎜であり、最大径が6.2㎜あって5㎜以上であり、Xの年齢、Xの右脳動脈瘤が多発性のものであることから、Xに手術適応があるとしたYの判断は当時の医療水準に照らして不合理とはいえない。」と判示し、推奨される指針を示しているはずのガイドラインを基に医療水準を判断している。
結果的には冒頭事案について医療側の過失を否定しているのではあるから、医療側弁護士である筆者が異議を唱えるのもおかしなことではあるが、臨床実務では最大径が5㎜前後より小さい場合でも破裂のリスクに備えて手術する場合も少なからず存在するのであって、その場合に合併症が発生して裁判に進展した場合には、裁判所は、上記ガイドラインを基準にして、手術適応がないのに手術をした過失があると判断してしまいかねないのが現在の医療裁判の現状であることにご留意いただきたい。
(7) 医療側弁護士と患者側弁護士の見解の相違
我々医療側弁護士は、「医療側がガイドラインの精度を高めようとしているのは、無駄な医療を撲滅しようとしているのに対して、法曹側は、過去に行われた医療行為が正しいか間違っているかの判断基準としてガイドラインを取り込もうとしている。」と主張し、裁判所のガイドラインの使用の仕方に警鐘を鳴らしているが、裁判所の考えを変えることは難しい。何故ならば、医療側もガイドラインに記載された治療方法が、標準的な治療方法であることを否定することはできず、裁判所が、標準的な治療方法を策定するためにガイドラインを用いることを完全に拒否することは理論的に不可能だからである。
医学的素人である裁判所としては、標準的治療方法を示すガイドラインからはずれた治療法について、患者側に対して「これは医学的に全く問題のない治療法です。」とは言いづらい。ましてや、遺族や重篤な後遺障害が残った患者の前では、尚更であろう。
こちらも医学的素人である患者側弁護士の立場では、患者が、「診療ガイドラインと異なる治療をされたことは医療過誤では?」と相談してきた場合に、明確な根拠がない以上説得する手段がない。医療過誤の可能性を否定できない以上は、委任を受けて損害賠償請求を行わざるを得ないことになってしまう。
(8) かくして、ガイドラインは、無駄な医療を撲滅しようとする作成者の意図とは全く異なる場面で独り歩きしてしまっているのが医療裁判の現状である。
裁判所は、「ガイドラインを作る側は、ガイドライン作成の目的が字面で分かるように書いていただきたい。」と希望しているので、ガイドライン作成に携わる医師の方は、ガイドライン作成が医師の過失を判断する目的ではないことや、仮にガイドラインの内容から外れたとしても医療界から見て問題ある治療とはいえないことを明記すべきであると考える。
某医大教授のX先生のシンポジウムの中での発言内容が印象的である。
「医療裁判が医療者にとっても納得がいくようにするためには、医療者が努力しないとなかなかできない。法曹界の方に棚上げしても決して良くならない。」
また、X先生は、以下の発言もしておられる。「一般論を述べますと、医者の中に経験していないのに実は経験しているがごとくにお話になる方がいらっしゃる。これは特に学会の上層部とか何か権威のありそうな教授の方に多いのですが、何でも知っているような顔をして言ってしまう。それが混乱を招いている。
結局医療者がきちんと鑑定するなり、分からないことは分からないと言うべきなのに言わないようなところから、どうも問題が発している面もあると思います。我々は、医療裁判がうんぬんで、萎縮医療になるんだとか何とか言っていますが、問題のもとは医療者が作っている面があると思うんですね。」
(9) 医療水準は、最終的には判決という形で裁判所が決定することになると上述したところであるが、決定するまでの過程には医療者が深く関与している。
医療裁判は、患者側対医療側の争いではなく、実は、医療側対医療側の争いなのである。
- 最後に
医師の過失についての法曹界の議論に対する、「どこまでが合併症で、どこからが過失なのか?」、「法的にどうかは置いておいても、医療としてはその段階でそういう対応をすべきだったということは、医療関係者、医療従事者の中にコンセンサスがある。」という医療側の疑問は、患者にとって不幸な合併症が発生した場合に、医師が責任を負うべきか否かを決定するに際して実に重要な指摘であると考える。
札幌市医師会医事紛争処理委員会は、これまで医療機関と患者の間に立って、実に多くの医療を巡る紛争を裁判前に解決してきたが、解決できた要因として、委員会が医療側の責任の有無(説明のあり方も含む)を判断するに際して、同じ医療関係者のコンセンサスに基づいて行うことで、医療側と患者側双方の納得を得られたことが挙げられる。医療を巡る紛争は、裁判例に基づいた法的過失の有無というだけではなく、当該医療行為が同じ医療従事者の視点からどのように評価されるのか、という観点からも議論することが紛争解決のために有益である。私は医療界と法曹界の相互理解が今後益々深まることを念じているが、現在の裁判所の基本的な思考方法を見る限り、医療を巡る紛争は裁判になる前に同委員会の仲裁で解決することが、医療側にとって最良の選択肢であると考える。
![]()