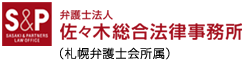講演日 令和元年11月7日
札幌市医師会医療安全研修会
医薬品投与と医師の注意義務
~医療界と法曹界の相互理解を深めるために(その2)~
- はじめに
医師と法律家との間には思考方法や用語の理解について食い違いがあり、医療を巡る紛争解決のためには、医師と法律家との間に共通の基盤や相互理解が形成される必要がある。
近年、各地で医療界と法曹界の相互理解を深めるために、シンポジウム開催等さまざまな取り組みがなされているところであり、昨年に引き続き、医療界と法曹界という2つの専門分野で、医療事故を接点として現れる思考方法などの相違点について認識を新たにしていただくことを目的に、講演させていただきたい。
-
医師の診療行為によって悪しき結果が発生したというだけでは、医師が責任を負うことはない。これが「過失責任主義」であり、民事上の責任の発生要件は、①過失(注意義務違反)ある診療行為の結果、②悪しき結果+損害が発生し、①と②の間に因果関係があることである。そして、医師の注意義務の具体的内容は、ア 医療水準に見合った医療行為を行うこと(医療水準は、医師が個々の患者に対して負っている診療上の注意義務を法的に判断する際の基準である。)、イ 患者の自己決定権を侵害しないこと、の2つであるが、診療行為当時の医療水準を認定するための資料として、裁判所は、診療ガイドラインを、策定時点における望ましい治療、あるいは標準的治療法を示す権威あるものと考えて重視していることは、昨年の講演でも説明したとおりである。
今年の講演テーマである、「医薬品投与」については、「診療ガイドライン」に加えて、薬事法52条の規定による法定文書である「医薬品添付文書」が、診療行為の過失判断の際の重要な証拠となるが、「医薬品添付文書」については2つの最高裁判決の内容を把握しておく必要がある。
- 一つ目は、最高裁第3小法廷平成8年1月23日判決である。
昭和49年、虫垂炎に罹患した患者X(当時7歳5か月)が、Y病院で虫垂切除術を受けたところ、手術中に心停止に陥り、蘇生はしたものの重大な脳機能低下症の後遺症が残った。Xに対し使用された麻酔剤(0.3%のペルカミンS)の副作用として、麻酔剤注入後に血圧低下があることはかなり古くから知られており、昭和30年代にはこれによる医療事故も多発したため、腰椎麻酔中は「頻回」に血圧の測定をする必要があるということ自体は臨床医の間に広く認識されていたが、「頻回」とはどの位の間隔をいうのかは一致した認識があったとはいえず、昭和47年から、ペルカミンSの添付文書に麻酔剤注入後10分ないし15分までの間、2分間隔で血圧の測定をすることが注意事項として記載されるようになった。しかし、本件手術が行われた昭和49年当時の医療現場では、必ずしも2分間隔での血圧測定は行われておらず、5分間隔で測定すればよいと考える医師もかなり存在し、本件事案でも5分間隔で血圧測定していたことが患者側から過失と指摘されていた。一審と控訴審は、当時の医療慣行に従っていたことから、当時の医療水準を基準にする限り医師に過失があったということはできないと判断した。しかし、最高裁は、「医薬品の添付文書(能書)の記載事項は、当該医薬品の危険性(副作用等)につき最も高度な情報を有している製造業者又は輸入販売業者が、投与を受ける患者の安全を確保するために、これを使用する医師等に対して必要な情報を提供する目的で記載するものであるから、①医師が医薬品を使用するに当たって右文書に記載された使用上の注意事項に従わず、②それによって医療事故が発生した場合には、③従わなかった特段の合理的理由がない限り、当該医師の過失が推定されるものというべきである。」「医師は一般にその能書に記載された2分間隔での血圧測定を実施する注意義務があったというべきであり、仮に当時の一般開業医がこれに記載された注意事項を守らず、血圧の測定は5分間隔で行うのを常識とし、そのように実践していたとしても、それは平均的医師が現に行っていた当時の医療慣行であるというにすぎず、これに従った医療行為を行ったというだけでは、医療機関に要求される医療水準に基づいた注意義務を尽くしたものということはできない。」と判示した。
つまり、現在の医薬品添付文書(以下「添付文書」)についての裁判所の考え方は、「医療用医薬品の場合には、医薬品の投与を受ける患者の安全を確保するため、これを使用する医師等に対して必要な情報を提供する目的で、当該医薬品の効能や危険性につき最も高度な情報を有している製造業者又は輸入販売業者に使用上の注意についての記載を義務付けている。そうであれば、医薬品を使用する医師としては、特段のことがない限り、添付文書に記載された注意事項に従って医薬品を使用すべき義務がある。」というものであり、医師は添付文書に記載された注意事項を必ず遵守しなければならないものではないが、それに反する措置をとった場合にはその合理的な理由を明らかにする必要があることになる。
我々医療側弁護士は、「①添付文書は、製造業者又は輸入販売業者が責任を問われないようにするため、わずかでも危険性があれば使用上の注意事項に記載しており、それに従っていると、重症患者や緊急を要する患者等に処方する薬が無くなる。②併用禁止や併用注意という記載がされていても、いろいろな病気を併せ持っている患者には併用せざるを得ないことがある。③当該患者の病態や体質等に応じて、当該医薬品の効用と副作用を踏まえて処方するのは医師である。添付文書が当該患者に対する医師の判断に優先するのは不当である。」と主張しているのであるが、残念ながら診療ガイドライン同様に、裁判所の考えを変えるに至っていない。
-
ところで、多くの文献では、医薬品投与の際の医師の注意義務について論じる場合に前記最高裁判決を引用しているが、実はこの判決には注意義務だけではなく、過失と結果発生との間の因果関係の問題も存在する。つまり、仮に血圧測定を2分間隔ではなく、5分間隔でしていたことが過失であるとしても、その差は、最大で3分であり、2分間隔で血圧を測定していると、より早期に状態の悪化を知ることができて後遺障害は残らなかったといえなければ、因果関係は認められず、医師が損害賠償義務を負うことにはならないからである。
この点について、前記最高裁判決は、「本件手術を介助していた看護師らが患者の異常に気付かなかったからといって、血圧の測定をしても血圧低下等を発見し得なかったであろうといえないことは勿論である(2分間隔で血圧を測定しなかったという医師の注意義務の懈怠により生じた午後4時40分から45分にかけての血圧値の推移の不明確を当の医師にではなく患者の不利益に帰することは条理にも反する。)。患者の血圧低下を発見していれば、医師としてもこれに対する措置を採らないまま手術を続行し、虫垂根部を牽引するという挙に出ることはなかったはずであり、そうであれば虫垂根部の牽引を機縁とする迷走神経反射とこれに続く徐脈、急激な血圧降下、気管支痙攣等の発生を防ぎ得たはずである。」と判示して、因果関係を認めているが、本事案で2分おきに血圧測定を行っていれば、後遺障害が残らなかったといえるかは非常に疑問である。
因果関係の立証についての裁判所の考え方は、最高裁第2小法廷昭和50年10月24日判決(ルンバール事件)で示されたとおり、「訴訟上の因果関係の立証は、一点の疑義も許されない自然科学的証明ではなく、経験則に照らして全証拠を総合検討し、特定の事実が特定の結果発生を招来した関係を是認しうる高度の蓋然性を証明することであり、その判定は、通常人が疑を差し挾まない程度に真実性の確信を持ちうるものであることを必要とし、かつ、それで足りるものである。」というものである。つまり、因果関係の立証は、過失行為と結果発生との間に高度の蓋然性があることが認められることが必要であるが、因果関係の機序を医学的に明らかにすることが求められているわけではなく、間接事実による推認によって因果関係を立証することが可能であるというのが裁判所の考え方である。ちなみに、「高度の蓋然性」というのは、あえて数字に表すと、80%程度確かであるという状態であり、99.9%間違いないといえるだけの確証は不要であるし、逆に6分4分程度の場合には因果関係なしになるのである。
法律家は、医師の方が、「因果関係が否定できない。」と言われると、「否定できない」→「因果関係はある」と受け取りがちである。しかし、医師の方にとって「因果関係は否定できない」という言葉は、「因果関係がゼロだとは断定できない」→「否定はできない」といった論理の場合が多く、強いてパーセントで言ってくださいというと「0.01%」だとか「0.1%」という数字が出てくるが、これは、法曹にとっては驚きであり、0.1%では、「高度の蓋然性」どころか「相当程度の可能性」すら存在せず、「因果関係は全く存在しないといってよい」と考えるのが、文科系出身の普通の法律家の思考なのである。
因果関係について裁判所の考え方をまとめると、以下のように整理できる。
なお、「保護法益」とは、「法令によって保護される利益」である。
- ① 過失と死亡、後遺症等との間の因果関係が高度の蓋然性をもって認められる場合→患者の生命または身体の保護法益を侵害した。→財産的(逸失利益)、精神的損害(高い額の慰謝料)が認められる
- ② ①の高度の蓋然性は認められないが、過失がなければ、死亡しなかった、後遺症が残らなかった相当程度の可能性(裁判官も明言しないが、裁判例に照らすと大体20%程度以上80%未満と考えられる)が認められる場合。→相当程度の可能性という保護法益を侵害→精神的損害(低い額の慰謝料)が認められる。
- ③ 相当程度の可能性もない場合(20%未満と考えられる)にはゼロ。
但し、当該医療行為が著しく不適切なものである場合には、適切な医療行為を受ける期待権という保護法益を侵害したものとして精神的損害(低い額の慰謝料)を認める余地がある。
- ところで、「添付文書に従わなかった特段の合理的理由」が認められる場合とはどのような場合であろうか
東京地裁平成25年9月12日判決は、添付文書上うっ血性心不全患者に対して禁忌とされていたメインテートの投与の過失の有無が争点となった事案である。東京地裁は、臨床現場では、慢性心不全患者に対する効能・効果から、メインテートが使用されていることや、2005年ガイドラインでは、頻脈性心房細動を合併した心不全の場合、β遮断薬がclass〈1〉(エビデンスから通常適応され、常に容認される。)とされており、実際に、平成23年5月には、メインテートについて、慢性心不全に対する効能・効果及び用法・用量が追加承認されるに至っていることなどの事実を総合して、当時の添付文書に反する投薬ではあったものの、投薬に合理的な理由が認められると判断して、過失を否定している。東京地裁の判示内容を見ると、たんに、診療ガイドラインに基づいた投与というだけでは「特段の合理的理由」にはならず、臨床現場での使用実績等の事実等も考慮した合理的エビデンスの存在が必要と考えられる。
- もう一つの最高裁判決は、最高裁第2小法廷平成14年11月8日判決である。
Y病院(精神病院)に入院中に治療のため複数の向精神薬の投与を受けた患者Xが、医師の投与した薬剤のうちフェノバールによってSJSを発症し失明した。XはY病院に入院中の昭和61年3月20日に全身の発赤、発疹、手掌の腫脹が認められ、同年4月15日までY病院で診察を受け、その後別の病院に転院したが、SJSを発症したのは同日以降のことであった。
本件当時のフェノバールの添付文書には「使用上の注意」の「副作用」の項に
「(1)過敏症ときに猩紅熱様・麻疹様・中毒疹様発疹などの過敏症状があらわれることがあるので、このような場合には投与を中止すること。(2)皮膚 まれにSJS、Lyell症候群があらわれることがあるので、観察を十分に行い、このような症状があらわれた場合には、投与を中止すること」と記載されていた。前記最高裁判決は、「精神科医は、向精神薬を治療に用いる場合においてその使用する向精神薬の副作用については、常にこれを念頭において治療に当たるべきであり、向精神薬の副作用についての医療上の知見については、その最新の添付文書を確認し、必要に応じて文献を参照するなど、当該医師の置かれた状況の下で可能な限りの最新情報を収集する義務があるというべきである。本件薬剤を治療に用いる精神科医は、本件薬剤が本件添付文書に記載された本件症候群の副作用を有することや、本件症候群の症状、原因等を認識していなければならなかったものというべきである。本件においては、3月20日に薬剤の副作用と疑われる発しん等の過敏症状が生じていることを認めたのであるから、テグレトールによる薬しんのみならず本件薬剤による副作用も疑い、その投薬の中止を検討すべき義務があった。すなわち、過敏症状の発生から直ちに本件症候群の発症や失明の結果まで予見することが可能であったということはできないとしても、当時の医学的知見において、過敏症状が本件添付文書の(2)に記載された本件症候群へ移行することが予想し得たものとすれば、本件医師らは、過敏症状の発生を認めたのであるから、十分な経過観察を行い、過敏症状又は皮膚症伏の軽快が認められないときは、本件薬剤の投与を中止して経過を観察するなど、本件症候群の発生を予見、回避すべき義務を負っていたものといわなければならない。」と判示し、たんに添付文書に従っているだけでは足りず、添付文書に記載されていない新規の副作用等が紹介されている等の最新情報があれば、それを踏まえた薬物治療を検討しなければならないというのが裁判所の考え方なのである。つくづく医師という職業は本当に大変なお仕事であるとの思いを禁じ得ない。
- 医師の方から質問を受けることが多いのが、患者さんを診察しないで投薬することの是非である。医師法20条には、無診察治療の禁止が規定されており、100年以上も前の、大審院大正3年(西暦1914年)3月26日判決は、「医師法第5条(*現在の第20条)に依れば医師は自ら診察せずして治療を為すことを得ざるものなれども治療前既に診察を為し之に因りて将来の病状を判断し一定の期間内連続して数次に一定の薬剤を授与し治療を為すことの計画を定めたる場合の如きは前回の診療に基き治療を為すも之を指して診察を為さずして治療を為したるものと云うを得ず」と判示し、治療計画を定めている場合には、無診察投薬が認められる場合もあるとしている。
大阪地裁平成30年3月1日判決は、「 医師法20条は、医師は、自ら診察しないで治療をしてはならない旨規定するところ、その趣旨は、医師自ら診察を行わなければ、患者の心身の状況を正確に知ることができず、症状に応じた適切な治療ができないことになり、ひいては患者の生命身体に不測の被害を及ぼすおそれがあるので、このような事態を防止することにあると解される。このような同条の趣旨及び文言に照らすと、外来の患者につき医師が診察することなく医療機関が治療を行うことは、原則として、同条が禁止する無診察治療に該当するが、例外的に、医師が患者を診察し、これによってその将来の病状を判断し得る場合において、一定の期間内に連続して数次にわたって一定の薬剤を投与するなどの継続的な治療を行う計画(以下「継続的治療計画」という。)を定めたときは、その計画に基づく治療は、毎回の医師の診察なく行われても、同条が禁止する無診察治療には該当しないと解するのが相当である(大正3年大審判参照)。」と判示しており、大審院判決と同じく継続的治療計画が定められている場合の無診察治療を認めている。
しかし、大阪地裁は、医師の診察により継続的治療計画が定められている場合であっても、患者の病名、症状及びその推移、治療の経緯、薬剤やその治療行為自体の危険性など諸般の事情に照らし、医師が治療の度に診察しないことにより患者の生命身体に重大な被害が生ずるおそれがある場合には、毎回の医師の診察なく治療を行うことは許されないというべきであると結論付けているので、結局のところ、現在の裁判所の考え方によれば、継続的なリハビリや副作用の発現リスクが極めて低い薬剤(そのような薬剤が存在するかは疑問であるが・・・)投与以外の治療は禁止されていると考えるべきである。
無診察投薬を求める患者に対しては、法律上、無診察治療が禁止されていて、違反行為には刑事罰(罰金50万円)が科されることや保険医療機関の指定を取り消される恐れがあるので(大阪地裁の事案は、無診察投薬等の診療報酬不正請求を理由に保険医療機関の指定取消処分を争った事案である。)、無診察投薬は厳にお断りすることを受付職員が説明できるようにしておくべきである。
- 医師の注意義務には、患者の自己決定権を侵害しないことも含まれる。これは、患者は治療の容体ではないのであって、医師は人間を治療していることから導かれる。患者が人間である以上、医師は患者の人格を尊重し、患者の同意を得て治療を行う必要があることを忘れてはならない。
退院の際に、添付文書によると0.1%未満の確率で中毒性表皮融解壊死症が発症する危険性がある薬剤を処方した事例で、高松高裁平成8年2月27日判決は、「患者に対して投薬の必要がある場合、その薬剤の選択については、担当の医師が総合的な診療方針のもとに、最良と考えられる薬剤を決定すべきであって、その点については医師の裁量が認められるということができる。そして、薬剤の投与に際しては、時間的な余裕のない緊急時等特別の場合を除いて、少なくとも薬剤を投与する目的やその具体的な効果とその副作用がもたらす危険性についての説明をすべきことは、診療を依頼された医師としての義務に含まれるというべきである。この説明によって、患者は自己の症状と薬剤の関係を理解し、投薬についても検討することが可能になると考えられる。」「副作用の発生率が極めて低い場合であっても、その副作用が重大な結果を招来する危険性がある以上は、投薬の必要性とともに副作用のもたらす危険性を予め患者に説明し、副作用の発症の可能性があっても、その危険性よりも投薬する必要性の方が高いことを説明して理解と納得を得ることが、患者の自己決定権に由来する説明義務の内容であると解される。」と判示している。
現在の裁判所の考え方によれば、発生頻度が高いもの(発生確率が1.0%以上)についての説明は当然であるが、発生頻度が低いものの中でも、生命の危険があるもの、不可逆的なもので日常生活に支障をもたらす可能性のあるものについては、説明義務の対象となることに留意し、薬物療法の最終責任者はあくまでも医師であることを踏まえて、副作用の説明に注意を払う必要がある。
医師の方から相談いただくことが多いのは、まれにしか生じない重大な副作用についての説明義務である。説明義務は、患者の自己決定権の前提となるものであるから、まれであっても重大な副作用については説明する必要はあるが、それを強調すると患者が怖がって医師が必要と考える投薬を拒みかねない。かような場合には「可能性としてゼロではないが、至極まれであって、まず生じることはない。」という説明で足りる。医療訴訟においては、まれな副作用が生じた場合に説明義務違反を問われることがあるが、可能性として予め考えられる副作用であれば、全く説明していなかったのであれば説明義務違反が問われることもありうるが、まれであることを強調した説明であったとしても、その説明内容は誤りとはいえないから、説明義務違反は認められない。
そして、説明したことをカルテに記載しておく必要がある、昨年の講演でも説明したとおり、医師は、「説明したことまでは、カルテに記載していないが、きちんと説明をしている。」と考えるが、裁判所は、「説明したという記載がないのは、医師が説明をしていないのではないか。書くべきことが書いていなければ、それはなかったのではないか。」と考えることに留意すべきである。
![]()