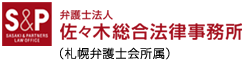- トップページ
- 取扱業務
- 1.企業法務
- 各種文書の作成
- 労働事件
- 倒産処理事件 [ 事業再生等 ]
- 法務監査 [ 法務DD ]
- 2.法人設立
- 3.民事事件
- 各種契約に伴う紛争
- 離婚
- 相続
- 後見
- 損害賠償請求
- 4.行政関係
- 5.医療関係 [ 医療事故等 ]
- 6.教育・学校関係
- 7.知的財産法関係
- 8.刑事事件
取扱業務
相続について
- 相続とは、被相続人が死亡することにより、一定の親族関係にある者が被相続人の財産に属する一切の権利義務を承継することをいいます。相続の対象となる遺産の分割手続は、遺言、遺産分割協議、調停、審判によって行われます。
当事務所は札幌に拠点を構えておりますが、これまで札幌市内・近郊以外でも北海道全域で多くの相続に伴う紛争に関与してまいりました。しかし、遺産分割協議や調停は非常に時間がかかりますし、各相続人それぞれに相続分や取得すべき遺産の内容について、それなりに過去の経緯に基づいた言い分がありますので、調整が大変であるというのが実感です。
そこで、相続分や遺産の分割方法を定めた遺言書を作成されることをお勧めします。一度遺言書を作成したら二度と変更できないと思い込んでいる方が多いのですが、民法1022条は、「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。」と規定しておりますので、遺言書作成後に親族間の人間関係に変更があるなどの理由により、いつでも自由に遺言を変更できるのです。
ただ、遺言の自由を放任すると、被相続人に依存して生活してきた人の経済的基礎を失わせる場合があるため、日本の民法は、たとえ自己の財産であってもすべて自由に処分する権利を認めておらず、法定相続人の遺留分を侵害しない範囲でのみ認められるという制約はありますが、それでも遺言が存在することによる遺族間の紛争防止の効果は大きいと考えます。 -
遺留分とは、遺言書によっても侵すことができない相続財産に対する割合であり、民法は兄弟姉妹以外の法定相続人(配偶者、子、直系尊属)に遺留分を保証しています。
遺留分を侵害された法定相続人は、余分に財産を取得した法定相続人や遺贈(遺言によって第三者に贈与すること)された人に対して、侵害された遺留分に相当する財産を渡すように請求できます。たとえ遺言書があっても、遺留分侵害をめぐる紛争が起きる可能性が少なからず存在しますので、当事務所では、遺言書作成の相談を受けた時には、遺留分を害さないような内容にするか、あるいは紛争が起きないような方法を工夫しながら遺言書を作成しております。
遺言書の内容が特定の法定相続人を優遇する内容で、他の法定相続人の遺留分を侵害するものである場合、後日紛争が全く起きないようにする唯一の方法は、遺留分を侵害される側の法定相続人が、民法1043条に基づいて遺留分を放棄し、家庭裁判所から遺留分を放棄することについて許可を受けることです。ただ、この手続きを行うためには、遺留分を侵害される側の法定相続人が遺言書の内容や放棄によって受ける不利益内容を十分理解した上で放棄することを決める必要があります。
他に、遺言者が遺言書とは別に、法定相続人宛の手紙(特定の法定相続人に多く遺産を渡す理由や自分の遺言に従って欲しい旨の希望など)を書いておいて、遺言者が死亡した時点で遺言保管者から渡して、法定相続人の理解を求める方法などがありますが、残念ながら、当事務所のこれまでの経験からは、遺留分の放棄手続き以外には、遺留分侵害をめぐる紛争発生を完全に防ぐことはできないというのが現実です。
-
民法に規定されている遺言の種類は、大きく分けると、普通方式の遺言と特別方式の遺言の2種類に分けられます。実際に多く利用されるのは、普通方式の遺言のうちの自筆証書遺言と公正証書遺言です。
自筆証書遺言は、遺言者が遺言内容全部、日付、氏名を、すべて自分で書かなくてはなりませんので、たとえ簡単な内容であっても、記載内容に間違いがあったりすることが散見され、場合によってはせっかくの遺言が無効となってしまう場合もありますし、公正証書遺言と異なり家庭裁判所で検認手続を受ける必要がありますので、あまりお勧めできません。
先日も、札幌近郊のある施設入居者の方がお書きになった自筆証書遺言の検認手続きを行ったところ、遺言の日付が、「平成」ではなく「平正」となっており、検認手続きは無事に終えましたが、いざ遺言に従って銀行預金の払い戻しを受ける段階で、銀行担当者から疑問の声が出されるということがありました(関係者の証言により間違いなく作成年を特定できることを説明して、無事に納得していただきました。)。
公正証書遺言とは、遺言者が公証人役場に赴いて、公証人に対して遺言の内容を話し、それを公証人が確認して公正証書として遺言を作成する方式ですが、遺言書の検認手続きも不要であり、遺言書の形式面や遺言時の意思能力の有無などから後になって無効される確率は、ほとんどなく、極めて安全かつ確実な方式といえます。遺言者が公証人役場まで出向くことが困難な場合には、公証人に施設まで出向いてもらい、施設の部屋の中で遺言書を作成することも可能ですし、費用も意外と安いものです。
最近の日本は無縁社会化しており、施設入居者に親族が存在しなかったり、親族は存在するものの、縁は切れていて、入居者が自分の全財産を施設に遺贈することを希望する場合が増加しておりますが、かような場合には公正証書遺言をお勧めします。
- 相続問題の相談例
私は、妻と子一人がおり、両親は既に他界しており、私の兄弟が2人おります。私は、現在会社を定年退職しておりますが、現在住んでいる家及び土地、その他に預金が5000万円あります。私は、現在は健康なのですが、将来認知症になったりして判断能力が不十分となった場合、妻は私の面倒は見ないと言っておりますし、子は既に独立し音信不通状態であることから、施設に入所したいと考えており、さらに、私が死亡した場合、全ての財産を私が入所した施設やお世話になった人に譲りたいと考えております。このような場合、法律上どのような方法をとるのが良いのかアドバイス願います。まず、あなたが、将来認知症になるなどして、施設入所の手続きを自分で行うことができなくなった場合に備えて、任意後見契約を締結することをお勧めします。
任意後見契約は、あなたが精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害等)により判断能力が不十分な状況になったとき、自己の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務の全部又は一部の代理権を任意後見人に付与する契約です。
あなたのように、奥さんや子供があなたの面倒をみない、つまり後見人となることが期待できないときには、予めこの任意後見契約をしておくことが有益です。
なお、任意後見契約は、公証人の作成する「公証証書」により締結することが必要です(その後、公証人は任意後見契約の登記を法務局へ嘱託します。)。
その後、あなたが、精神上の障害により判断能力が不十分となった場合は、本人、配偶者、四親等内の親族又は任意後見受任者は、家庭裁判所に対し任意後見監督人の選任の申立をします。そして、家庭裁判所が本人の判断能力が不十分な状況であると認めたときは、任意後見監督人を選任し、任意後見契約の効力を発生させることになります。
任意後見契約の効力が発生すると、契約内容にもよりますが、任意後見人は、あなたの財産管理に関する法律行為、日常生活や療養看護に関する法律行為も行う権限と同時に、介護契約、施設入所契約などをあなたの意思や利益に適うように行なう義務があります。
あなたのように、親族の中に適切な相手がいない場合には、任意後見人を法律の専門家である弁護士や弁護士法人に指定されるのが安心です。
次に、あなたの死亡後に、あなたの希望する相手に財産を譲るためには、任意後見契約とともに、遺言を作成されることをお勧めします。
あなたの財産は、法定相続人である妻と子が、それぞれ2分の1づつ取得することとなるた
め、将来認知症等が発症してしまった場合、残念ながら、あなたの相続に関するご意向は反映されない可能性が高いといえるからです。
あなたは、お亡くなりになった場合、相続財産を法定相続人ではなく、第三者に譲りたいとのことですので、遺言において、その第三者に遺贈しておかなくてはなりません。
遺贈とは、遺言によって自らの財産を無償で他人に与えることです。遺贈によって利益を受ける人を受遺者といいます。
受遺者は、権利能力者であれば、自然人でも法人でもなることが出来ますので、施設やお世話になった方へ財産を譲るという、あなたのご意向に沿った財産の移転ができるでしょう。
もっとも、全ての財産を、第三者に譲るという内容の遺言には、少し注意を要します。
なぜなら、あなたの直系尊属、直系卑属、配偶者には、相続に関して法律上取得することが補償されている相続財産の割合が認められているからです。
これを「遺留分」といいます。
相続財産に占める遺留分の割合は、(1)直系尊属のみの場合は3分の1、(2)直系卑属又は配偶者の場合は2分の1と定められております。このように、遺留分とは、法定相続人が、相続財産を最低限取得できる権利であり、遺言によっても、この遺留分を完全になくすことはできないのです。
妻の遺留分は、法定相続分の2分の1、子の遺留分も法定相続分の2分の1ですから、あなたの場合、遺留分の合計は相続財産の2分の1となります。
全ての財産を第三者に譲ることについて、妻や子が不満をもたないのであればよいのですが、遺留分をめぐる紛争は珍しいものではありません。
遺言は、あなたが亡くなった場合、相続財産を誰に相続させるかなどを記載することで、あなたの最終的な意思を反映するとともに、相続に関する紛争を防ごうとするものです。
したがって、法定相続人と、あなたの財産を取得させたい第三者との間の紛争を未然に防ぐためには、この遺留分を考慮し、例えば、現金5000万円を第三者に譲り、土地と建物を妻と子に譲る、などの遺言内容とすることが考えられます。
なお、あなたの死亡後ではなく、生前に財産を第三者に贈与する、生前贈与という方法も考えられます。しかし、ここでも注意が必要です。
贈与に対しては、死亡する前の1年間まで遡って相続財産に加算されますし、あなたと贈与を受ける第三者が、その贈与によって、妻と子の遺留分に損害を与えることを知ってした場合は、1年前のものに限定されることなく相続財産に加算されるため、遺贈の場合と同様、遺留分の問題が生じる可能性があるからです。
実際に遺言を作成する方法としては、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」などがあります。
自筆証書遺言は、自筆にて記載する方法であるため、いつでも自由に作成できる点で簡便な方法といえますが、一方で、記載等に不備があった場合、希望どおりの効力を得られない可能性もあります。
公正証書遺言は、公証人が作成する公正証書によってする遺言で、公証役場で半永久的に保存されることから、証拠としては勿論、紛失、隠匿、改変等の危険が無いというメリットがありますので、公正証書遺言の作成をお勧めします。
そして、実際に作成した遺言を執行するため、遺言執行者を遺言にて指定されるのが良いでしょう。遺言執行者は、弁護士や弁護士法人を指定することができますので、法律の専門家である弁護士や弁護士法人を指定されると安心です。
以上