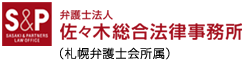- トップページ
- 取扱業務
- 1.企業法務
- 各種文書の作成
- 労働事件
- 倒産処理事件 [ 事業再生等 ]
- 法務監査 [ 法務DD ]
- 2.法人設立
- 3.民事事件
- 各種契約に伴う紛争
- 離婚
- 相続
- 後見
- 損害賠償請求
- 4.行政関係
- 5.医療関係 [ 医療事故等 ]
- 6.教育・学校関係
- 7.知的財産法関係
- 8.刑事事件
取扱業務
医療事故調査制度について
-
平成26年6月25日付で公布された改正医療法における医療事故調査制度に関する規定が本年10月1日から施行されている。公布から1年4ヶ月経過後の施行は一見長すぎるようにも思える。しかし医療事故の定義その他多くの内容について、医療法は公布後に作成される厚生労働省令(以下「省令」という。)に委ねているために、医療事故調査制度の具体的内容は、わずか1年弱の短期間の議論で作成されたものであり、医療法と省令についての解釈が必ずしも定まってはいないことに留意する必要がある。医療法や省令についての厚生労働省の解釈を示す通知についても同様である。そのため、各種ガイドラインの記載や各種講演会では、論者によって全く異なる解釈が自由に飛び交っているという実に不思議かつ憂慮すべき事態となっている。
医療事故調査制度は、医療法の定める医療事故については、医療事故調査・支援センター(一般社団法人日本医療安全調査機構が、本年8月17日付で同センターとして指定を受けている。以下「センター」という。)に報告することや院内事故調査を行うことをすべての医療機関(規模、有床、無床を一切問わない。)に義務づけた内容となっている。
本制度の対象となる医療事故は、従前厚生労働省が定義していた内容とは異なり、「①当該病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産であって、②当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかつたものとして厚生労働省令で定めるものをいう。」とされており、省令によれば、患者の死亡事案が医療事故に該当するか否かの判断は医療機関の管理者が行うこととされているため、有床、無床を問わず医療機関の管理者としては、本制度で報告義務を課される医療事故の要件について正確に理解しておく必要があるが、上述のように医療事故該当性自体についても、論者によって見解がまちまちであることに留意する必要がある。 -
①医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産
- (1)医療と考えられる行為の具体的内容は、厚生労働省の通知により、手術・処置・投薬及びそれに準ずる医療行為(検査・医療機器の使用・医療上の管理など)と規定されている。このような行為に起因して発生した事故が対象となる。
- (2)施設の火災、提供した医療に関連のない偶発的に生じた疾患による患者死亡は医療行為に起因するとはいえない。ただ転倒・転落に関する事故は、例えばリハビリ中に患者から目を離した際の転倒と、たんに患者が廊下を歩行している際につまづいて転倒したという場合では、前者は提供した医療に起因する疑いがあると言えるが、後者は通常そのようには判断できない。
- (3)そのため、単純に行為のみを外形的に判断するのではなく、治療行為の一環としての行為か否かという観点から判断することが重要となるが、現実には判断が微妙な事案も存在するであろうから、今後の事例の集約を待たざるを得ないと考える。なお、日本医療法人協会医療事故調運用ガイドライン作成委員会作成による平成27年5月30日付「医療事故調運用ガイドライン」最終報告書25頁には、「転倒・転落、誤嚥、隔離・身体拘束・身体抑制、褥瘡、食事・入浴サービスなどについては、それ自体は医療に当たりませんので、通常「医療行為に起因する死亡」要件に該当しません。しかし、投薬等、他の医療行為(特に積極的医療行為)が介在して死亡を起因したと管理者が判断した場合には、「医療に起因する死亡」要件に該当します。」と記載されており、転倒・転落に関する事故について医療起因性を狭く解していることが参考になる。
-
②管理者が予期しなかった死亡について
- (1)医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡のうち、以下のいずれにも該当しないと管理者が認めたものである。
- ⅰ 医療提供前に死亡が予期されていることを患者に説明したと認められるケース
- ⅱ 医療提供前に死亡が予期されていることを診療録その他の文書に記録されていたと認められるケース
医療行為では仮に万全な医療行為を行ったとしても何が起こるか分からないので、医療水準に従った適切な医療行為を行ったとしても予期せぬ死亡ということは不可避的に起こりうる。「予期」という言葉についての明確な定義は難しいが、「まさか亡くなるとは思わなかった。」という状況と考えられる(上記報告書21頁参照)。
ところで、外科手術、たとえば腎臓摘出術の際に縫合不全による腎動脈からの出血による循環不全で死亡したという事案の場合、縫合不全による出血という事象自体は特別なものではないので、縫合不全による出血がありうること、出血量等によっては死に至ることを、術前に患者に説明していたか、あるいは診療録に記載していた場合はどうであろうか。
省令の内容からすると、死亡を予期していたものとして、医療事故には該当しないことになるが、厚生労働省平成27年5月8日付通知には、「省令第1号及び第2号に該当するものは、一般的な死亡の可能性についての説明や記録ではなく、当該患者個人の臨床経過等を踏まえて、当該死亡又は死産が起こりうることについての説明及び記録であることに留意すること」と記載してあり、省令記載の要件が厳格化されている。上記通知によれば一般的に外科手術の際に縫合不全による出血がありうること、その結果死に至るという内容の説明や記載のみでは足らず、当該患者の病状や体質なども含めたうえでの説明や記載が無くてはならないことになりそうである。しかし「人間はいつか死にます。」とか「高齢のため何が起こるかわかりません。」だけでは、患者にとっても家族にとっても、それだけで死亡について「予期していた」と言われたのでは、到底納得できないであろうが、外科手術を受けること、その際の縫合不全による出血が起こりうることは、まさに患者の臨床経過等を踏まえての説明であるし、法律は国会の議決を経ており法律の文言には重みがあり、法律や法律の委任を受けた厚生労働省の命令である省令の文言を外れた解釈をすべきではないので(*通知は厚生労働省の法令についての解釈を示したものにすぎず、命令ではないのである。)、外科手術の内容等から死亡の可能性について説明していた場合には、死亡を予期していたと考えるべきであろう。
医療機関としては、この機会に、患者に対する医療行為に起因する死亡の可能性についての説明や診療録への記載について再検討すべきであると考える。 - ⅲ 事後的な医療従事者からの聴取などにより、医療従事者等が事前に死亡を予期していたと認められるケース。
事前に上記ⅰⅱの対応を行っていないものの、事後的な聴取により予期した形と判断された場合である。単身で救急搬送され、記録や説明の猶予がなく、かつ比較的短時間で死亡した場合や、過去に同一の患者に対して、同じ検査・処置等を繰り返し行ったため、説明や記録が省略された場合等、ⅰⅱの客観的証明がなされない場合を想定したものである。
- ⅳ なお上記報告書21頁では、薬剤の取り違えなどの単純過誤事例については管理者の予期した頻発する類型であるとして、制度の対象とならないとしているが、ここまで対象を狭くすることについては疑問がある。
- (2)医療を提供するにあたっては、医師は患者に適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めることとされていることや(医療法1条の4)、医師は診療したときは遅滞なく診療録に記載することとしている医師法24条の規定に基づき、医療事故調査制度施行後は、医師はこれまで以上に患者に対するインフォームドコンセント、特に死亡の可能性についての説明を心がけ、同時に充実した診療記録を作成するよう努めることが要請される。検査や手術の承諾書には死亡の可能性がゼロではないことを記載し、きちんと患者に説明し、同時に検査や手術を受けない場合のデメリットについても説明して、患者に検査や手術を受けることについての選択肢を示すことが必要である。死亡の可能性について説明すると患者が検査や手術を受けなくなることを懸念する医師も存在するが、何よりも患者の自己決定権を尊重すべきことを忘れてはならない。
- (1)医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡のうち、以下のいずれにも該当しないと管理者が認めたものである。
-
医療機関に報告義務が課される医療事故の内容については上記のとおりであるが、ここで改めて医療事故調査制度の概要及び手続の流れについて説明したい。
- (1)医療機関において死亡事例が発生した場合、まず医療機関の管理者が法律上の医療事故に該当するかどうかを判断し(①)、医療事故に該当すると判断された事案について、あらかじめ遺族へ説明したうえで(②)国が指定する民間組織であるセンターに報告することが求められている(③)。
なお、医療機関の管理者は医療事故に該当すると判断した場合にセンターへ報告しなくても罰則は科されない(罰則がないから報告しなくても良いという理屈にはならない。)。また、遺族が、「報告しないで欲しい。」と希望してもセンターへの報告義務は消滅しないことにも留意する必要がある。 - (2)報告した事案について、医療機関自身がその原因を明らかにするための調査を実施する(④)。今般の制度は医療機関が行う調査が制度の機軸となっていることから、各医療機関が責任を持って、当該事案における事実の経過等の原因調査を行うことが重要であり、このことが本制度の根幹である。
- (3)医療機関での調査が終了した後は、医療機関自らが遺族に対し調査結果を説明し(⑤)、センターへ報告する(⑥)。
- (4)センターは、報告された事例を整理・分析し、一般的な再発防止策の立案に取り組む。ただし、遺族又は当該医療機関が第三者の調査を求めた場合、センターは調査を行うことができる(⑦)。その場合、センターは院内調査の報告をもとに事実関係の整理及び医学的見地からの検証を行い、必要に応じて補完的な調査を行う(⑧)
- (5)このような過程を経て、センターがまとめた調査の結果は、医療機関及び遺族に報告される(⑨)。
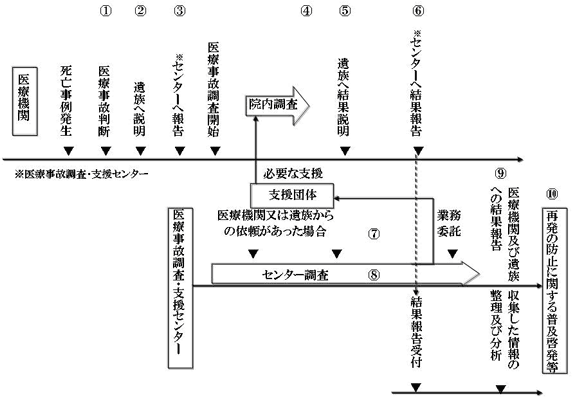
- (1)医療機関において死亡事例が発生した場合、まず医療機関の管理者が法律上の医療事故に該当するかどうかを判断し(①)、医療事故に該当すると判断された事案について、あらかじめ遺族へ説明したうえで(②)国が指定する民間組織であるセンターに報告することが求められている(③)。
-
医療機関は、まずは、上記①のとおり、医療事故に該当するか否かの判断をしなければならない。
判断主体は、医療機関の管理者であって、主治医や遺族でもなく、センターではない。管理者自らが診療に従事していない場合には、判断するに当たっては、当該医療事故に関わった医療従事者等から十分事情を聴取した上で、組織として判断することになる。
判断基準は、繰り返しになるが、以下のとおりである。
① 医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産か否か?
② 当該死亡又は死産を予期していたか否か?
小規模医療機関であって、自ら判断することが困難である場合には、センターや医師会等の支援団体に相談することとなる(厚生労働省作成のQ&A11参照)。
上記のとおり、医療法上の医療事故が発生した場合、医療機関は最低①と③の2回は遺族へ説明・対応することを余儀なくされるが、現実には、死亡事例が発生し、医療事故と判断する前の段階においても遺族に対して診療経過等を説明する必要があるから、実際には3回にわたって遺族への対応が必要となる。
また、医療機関はたんにセンターへ報告する義務を課せられるだけに留まらず、自らが責任を持って院内調査を行わなければならず、たとえ小規模な医療機関(医師1人の無床診療所と雖も例外ではない。)であっても院内調査義務は免責されない。この点において、医療機関自らの調査負担は少なくて外部一任に等しかった「診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業」とは全く異なることに留意する必要がある。上記Q&A16によれば、もちろんセンターや医師会等の各支援団体のバックアップは得られることにはなっているが、遺族への対応も含めて医療機関の負担は増大するといわざるをえない。 -
かように改正医療法によって設けられた医療事故調査制度により、医療機関の負担は重くなるのであるが、他方で医師法21条に基づく異状死の届出義務はそのまま残るし、刑事訴訟法、民事訴訟法の規定が制限されるわけでもない(注1)。医療機関は、院内調査結果を報告書にまとめてセンターに提出しなければならないが、この報告書を警察が捜索差押手続きによって強制的に入手する可能性は現行法上全く排除されていないし、民事訴訟における文書提出命令についても、事故調査制度では院内調査報告書がたんに院内における使用だけではなく、センターすなわち院外への報告を前提としていることや、通知が遺族の希望する方法で説明することを医療機関に求めていること等を考えるなら、今後裁判所が、院内調査報告書についてどのような取扱をするかは確定できない(注2)。
また、遺族に対しては書面ではなく口頭でも良いとされているが、遺族の要請に応じて院内調査報告書を交付した場合には、遺族側がどのように利用するかは全くの自由である(注3)。
そもそも異状死の届出制度と異なる制度の必要性、医療過誤の判断の専門性から警察の関与を制限することの必要性が叫ばれ続けてきて、新制度創設が待ち望まれてきたはずであるが、その新制度として登場した医療事故調査制度は、残念ながら多くの医療者の期待に全く応えていないと言わざるを得ないのである。 -
省令は「病院等の管理者は、当該医療従事者のヒアリング等を行って、医療事故の原因を明らかにするために情報の収集及び整理を行うことを定めており、さらに通知では「調査の対象者については当該医療従事者を除外しないこと」とされている。他方において通知では、「本制度の目的は医療安全の確保であり、個人の責任を追及するためのものではないこと」が明記されているし、上記のとおり院内調査報告書の民事・刑事における利用制限について、何ら法的担保はなされていない以上、医療機関は憲法38条で保障された黙秘権等医師個人の人権についての配慮を行う必要がある。具体的には、当該医療従事者の発言内容が、後日、民事・刑事裁判の証拠として使われる可能性があることを当該医療従事者へ教示しておく必要があるし、黙秘権の告知も必要である。それにもかかわらず、医療機関管理者は法令上医療事故原因を明らかにするための努力を強いられるのであって、医療従事者の人権を侵害せずに出来うる範囲で調査について努力するしかないことになる。
医療事故調査制度は、医療の安全を確保するために医療事故の再発防止を目的として、医療者の自立的な取組として、医療事故の調査、分析を行うことを根幹としているが、実は、他の関係法令との調整が全くできていないままスタートさせてしまったため、医療者、特に医療機関管理者にとっては実に厄介な制度なのである。
- 注1 Q&A24には、「報告書を訴訟に使用することについて、刑事訴訟法、民事訴訟法の規定を制限することはできませんが」と明記されている(本来であれば、「規定を制限することができますので、医療従事者は安心して報告書作成にご協力下さい。」と記載できるようにしてから、本制度をスタートさせるべきだったのである。)
- 注2 民事訴訟においても、大学病院における医療事故経過報告に対する文書提出命令の申立てについて、東京高裁平成15年7月15日決定は、「事情聴取部分については、民事訴訟法220条4号二所定の除外文書に当たるが、「この報告提言部分は、事故発生の原因、家族への対応、社会的問題発生の原因、今後への提言につき、詳細な事実経過とこれに対する評価を客観的に記述しており、本件医療事故の原因の究明、今後の防止策に大いに資するものといえる」等との理由から、たとえ内部の者の利用に供する目的で作成されたとしても、開示によって所持者の側に看過し難い不利益が生ずるおそれがあるものとまでは認め難い等として、報告提言部分の開示を認めている(判例タイムズ1145号298頁)。
- 注3 この点について、医療機関と遺族との間で証拠制限契約を締結することにより裁判では証拠として利用できなくすることができるとの考えがあるが、事故調査の結果が不明の状態の時に無制限に証拠としての利用を制限することは遺族側に予想し得ない不利益を一方的に課すことになり、かような契約は法的に無効となる。同様に、院内掲示で「院内調査の結果を証拠として使用することは認めません。」と掲示しても効力がないことに留意する必要がある。
- 注1 Q&A24には、「報告書を訴訟に使用することについて、刑事訴訟法、民事訴訟法の規定を制限することはできませんが」と明記されている(本来であれば、「規定を制限することができますので、医療従事者は安心して報告書作成にご協力下さい。」と記載できるようにしてから、本制度をスタートさせるべきだったのである。)
以上