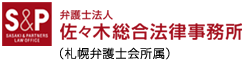- トップページ
- 取扱業務
- 1.企業法務
- 各種文書の作成
- 労働事件
- 倒産処理事件 [ 事業再生等 ]
- 法務監査 [ 法務DD ]
- 2.法人設立
- 3.民事事件
- 各種契約に伴う紛争
- 離婚
- 相続
- 後見
- 損害賠償請求
- 4.行政関係
- 5.医療関係 [ 医療事故等 ]
- 6.教育・学校関係
- 7.知的財産法関係
- 8.刑事事件
取扱業務
医療事故調査制度と異状死届出義務について
- 本年10月1日から施行された医療事故調査制度は、刑事訴訟法、民事訴訟法、医師法の適用を一切制限していないので、医療法の定める医療事故が発生した場合、医療事故・調査支援センターに報告する義務とは別に医師法21条に基づく異状死の届出義務はそのまま残ることになる。しかし、医師の間には、医師法21条に対する誤解がいまだに根強く存在するように思われるので説明しておきたい。
-
医師法21条の条文は以下のとおりである。
医師は、死体又は妊娠4月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、24時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。
法律を作るのは国会であるが、法律の条文の意味を最終的に解釈する権限があるのは最高裁判所である。そして、「異状死」の解釈については都立広尾病院で准看護師が誤って消毒薬を静注して死亡させ、病院長が医師法21条違反で起訴された事案(以下「本件」という。)についての判決内容を認識しておくことが不可欠であると考える。
本件は、慢性関節リウマチを患っていた当時58歳の女性の術後に血液凝固防止剤であるヘパ生を輸液すべきところ、誤って消毒液を輸液してしまったために患者が死亡したというものであり、明白な医療過誤事件である。 - 本件について、一審の東京地裁は、主治医が、①患者の病状の急変、②消毒液輸液という明白な医療過誤、③死亡診断時に患者の右腕に色素沈着の状態があることを認識していたことをもって、平成11年2月11日午前10時44分ころ、主治医は患者の死亡確認時に死体を検案して異状があるものと認識しており、病院長は翌日開催の病院の対策会議で主治医から報告を受けて認識していたにもかかわらず、24時間以内に警察に届出をしなかったとして有罪とした(東京地裁平成13年8月30日判決 判例時報1771号156頁)。
- それに対して本件控訴審の東京高裁は、医師法21条にいう死体の検案とは、「死因を判定するためにその死体の外表を検査すること」であるとして、平成11年2月11日午前10時44分の時点では、主治医が患者の右腕の色素沈着に気付いていたことについての証明が十分ではないとして一審判決を破棄し、翌日午後1時頃に実施された病理解剖に立ち会った際に、「患者の死体の外表を検査して検案を行い、患者の死体の右腕の静脈に沿って赤い色素沈着がある異状を認めたことが明らかである。」と判示し、病理解剖に立ち会った時点で異状を認めたものと認定した(病院長については、病理解剖終了後に、死体に異状がある旨の報告を受けたにもかかわらず届出しなかったことについて主治医と共謀したと判断されている。)。つまり、東京高裁は、死体の外表を検査し、外表に表れた異状を認識することが、医師法21条の「異状があると認めたとき」であり、患者の病状の急変や医療過誤の認識、死亡原因の不明の点などは医師法21条の問題とは切り離して考えるべきであると判示したのである(東京高裁平成15年5月19日判決 判例タイムズ1153号99頁)。
-
本件上告審である最高裁も、「医師法21条にいう死体の「検案」とは、医師が死因等を判定するために死体の外表を検査することをいい」と判示して、東京高裁判決を支持した(最高裁第三小法廷平成16年4月13日判決 判例タイムズ1153号95頁)。
従って、現在では、医師が死体の外表を検査して、外表面に異状を認めた場合に、異状死として届出義務を負うというのが裁判所の確立した考えであり、
同時に、医師法21条が要求しているのは異状死体があったことのみの届出であり、医療過誤があったことなどの報告を求めるものではないので、不利益供述の拒否権(自己負罪拒否特権)を保障する憲法38条1項にも反しないことになるのである。 -
ところで法律の条文解釈についての最終権限はないものの、医療を所管する行政庁である厚生労働省は、医師法21条の届出要件について、上記最高裁判決の立場とは異なり、医療過誤があった場合等死亡に至る過程が異状であった場合にも異状死の届出義務を負うという、およそ医師法21条の文言にも、自己負罪拒否特権を保障する憲法38条にも反する誤った解釈を長らく行ってきており、そのために医療機関は本来警察への届出を必要としない診療関連による死亡事故についても届出を行わざるを得ないという混乱が続いてきた。
平成24年10月26日に、ようやく厚生労働省医政局医事課長が医師法21条の解釈について「医師が死体の外表をみて検案し、異状を認めた場合に警察に届け出る」と発言し、平成26年6月10日には、田村憲久厚生労働大臣も上記と同じ内容を答弁し、医師法21条の解釈を巡る長い混乱に終止符が打たれたのであるが、厚生労働省は正しい医師法21条の解釈をもっと医療現場に周知させるべきであろう(日本医療法人協会平成27年5月30日付「医療事故調運用ガイドライン」最終報告書4頁末尾に同趣旨の意見が記載されている)。 -
厚生労働省が正しい医師法21条の解釈を徹底しないまま、制度創設意義がよく分からない医療事故調査制度を開始させてしまったために、医師の方から、「薬剤の量や種類を間違えて使用したという明白な医療過誤の事案の場合には、医療事故として医療事故・調査支援センターに報告することと併せて、医師法21条の異状死として警察に届け出るべきなのか?」という質問を受ける。しかし、都立広尾病院事件の場合には、消毒薬を輸液してしまったので死体の右腕の静脈に沿って赤い色素沈着があるという外表面の異状があり、そのために異状死としての届出義務が認められたのであるが、たとえばインスリンを誤って過量投与しても、外表面に異状はないはずであるから、たとえ明白な医療過誤であっても医師法21条に基づく届出義務は存在しない(このことは通常の過失であろうと故意・重過失の場合でも全く変わらない。)。
現実には診療関連死に医師法21条が適用されるケースは極めて希なのである。
医師が医師法21条に基づく届出義務を負うのは異状な死体を見つけた場合であって、異状死亡(医療過誤等による死亡)を見つけた場合ではないことをご注意頂きたい。
-
ところで、上記の事案の場合、過量投与が看護師のミスに基づくものである場合に、看護師に業務上過失致死罪(刑法211条)が成立する可能性があることから、異状死としてではなく刑事事件として届出すべきであろうか。当該医療に関与した当事者らには憲法38条1項で保障された自己負罪拒否特権があり、自首する義務はないから、業務上過失致死罪として警察に届出する義務はない。
届出義務はないとしても、届出するのが望ましいのであろうか。この点については議論が分かれるところかもしれないが、以下のように考える。
事故発生が、看護師の過失なのか、システムにあるのかを明らかにするのが今回の医療事故調査制度の目的なのであり(医療事故の原因を個人の医療従事者に帰するのではなく、医療事故が発生した構造的な原因に着目した調査を行うことが厚生労働省Q&Aに記載されている。)、まずは医療事故としてセンターに報告すべきであり、看護師の責任が確定していない段階で、看護師個人の責任追及のために、医療機関が警察に届出するのは時期尚早というものであろう。
日本経済新聞平成27年11月15日付朝刊で、フランス高等保健機関前理事長のローラン・ドゴース氏が、2009年にパリの小児科専門病院で看護師が成人向けの薬剤を誤って子供に注射したために死亡した事故について以下のように述べている。
「事故直後、警察は看護師を勾留した。メディアが大騒ぎし、誰もがこの看護師に罪があるとコメントした。だが、事故から1週間後、病院を運営していたパリ公立病院協会の責任者らが勇敢にも「責任は看護師ではなく、システムにある。」と明言したことで、本格的な事故調査につながった。調査では、様々な要因が分析された。なぜ成人向けの薬品がそこにあったのか。誰が持ち込んだのか。薬品のラベルには特別な表示がしてあったのか。室内の照明はラベルの文字が判読できるくらい十分に明るかったのか。他の薬瓶と外見が似ていたのではないか。看護師は過労状態ではなかったか・・・・・。(中略)それまで組織の責任者は、その場にいた人物に罪をなすりつけ、賠償と制裁を要求する被害者が「犯人」をつるし上げるのを容認してきたのでないだろうか。悲嘆に暮れ、同じ行為を繰り返す気など全くない看護師を追及するのは正しいことだろうか。(以下略)」
まずは、医療事故としてセンターに報告して、院内調査を行い、事故発生原因が、個人の過失だけによるものなのか、システムによるものなのかを十分見極めてから警察への届出について検討すべきであろう。遺族に対しては、医療法に基づいてセンターに報告済みであること、従って隠蔽の意図は全く存在しないことを丁寧に説明して納得してもらうことが必要である。
以上